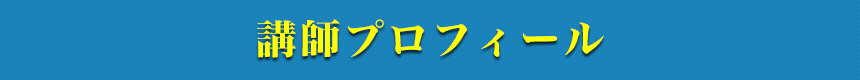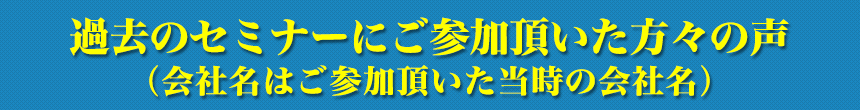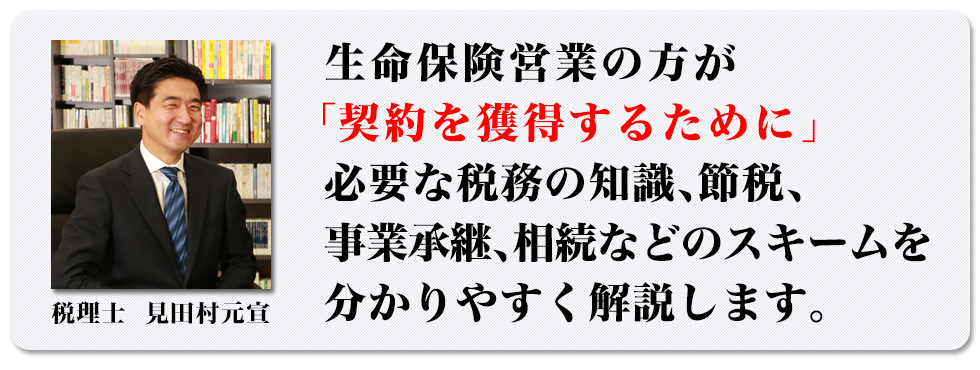
まずはダイジェスト動画をご覧ください(画面をクリックすると再生します)。
- 共有の株式は持分割合での議決権行使となる
- 遺留分侵害額の具体的な計算方法を確認する
- 生命保険は代償給付として認められるのか?
- 生命保険を活用して民法特例の合意を図る
- 死亡保険金が特別受益に該当した理由を考える
- 役員死亡退職金は相続財産か?固有財産か?

永吉 啓一郎 (ながよし けいいちろう)
弁護士法人ピクト法律事務所 代表弁護士
愛知県知多市出身。司法試験合格後、司法修習生、鳥飼総合法律事務所を経て、弁護士法人ピクト法律事務所を設立し、代表に就任。現在、300名以上の「税理士」が会員となっている「税理士法律相談会」を運営し、年間400件以上の相談を受けている。特に法務と税務がクロスオーバーする領域に定評があり、税理士と連携した税務調査支援、税務争訟対応、相続・事業承継対策、少数株主対策、税賠対応(税理士側)や税理士事務所内部の法的整備などを多く取り扱っている。また、税理士を対象とした研修講師や約3,000の税理士が購読する「税理士のための法律メールマガジン」等を通じて、税理士実務に必要な法律情報などを広く発信している。
主な著書に以下のものがある。
・「非公開会社における少数株主対策の実務〜会社法から税務上の留意点まで〜」(清文社)
・「民事・税務上の「時効」解釈と実務~税目別課税判断から相続・事業承継対策まで」(清文社)
・「企業のための民法(債権法)改正と実務対応」(清文社)
当日、セミナーにご参加頂いた方のアンケート(5段階評価)の集計結果です。


今日はありがとうございました。今、ちょうど自社株と遺留分のお話をさせて頂いているお客様がいて、とても参考になりました。段階的な対策は、お客様は取り入れやすいのではないかなと感じます。そして、遺留分の基礎的な事も含めてお話頂いたので、すごくイメージがしやすかったです。民法と税法でこんなにも違いがあるということもビックリでした。除外合意は、初めて知る知識でしたので新しい情報としてお客様にもお届けできそうです。改めて今日の復習もして、お客様のお役に立てていけたらと思います。


生前対策のない自社株の相続、後継者を受取人とする生命保険の活用事例として、例外的に「特別受益」に準じるので注意が必要となる事例は、とても大切と思いました。特に比率については裁判例があるので、生命保険を活用できると感じました。


実際に全く自社株対策をしていなかったオーナー経営者のお客様が急死し、認知症の妻と子2人が残された事例があり、多くの経営者にこの対策を伝える事はとても重要だと認識しました。民法特例がさほど周知されていないのも実感としてあり、中小企業を経営者の急死から守る手段としての生命保険の提案をより一層、進めたいと思います。


基本的なところから順を追ってお話いただいたので、大変わかりやすかったと思います。民法特例あたりは実際にあったことがないので、ややピンとこないところがあったものの内容としては何となくですが、理解はできて良かったです。


遺留分計算について様々な角度からの説明がわかりやすかった。民法特例制度について、普段は聞かない内容で参考になった。又、生命保険のかつようについても参考になった。


生前対策のない自社株の相続について、具体的に教えていただき理解が深まりました。準共有状態になるリスクを経営者にお伝えして生前対策を早めにしてもらうようにします。種類株や信託契約よりも、まずは自社株のみの一行遺言の作成もお勧めしていきます。後半の遺留分についても たいへん分かりやすくまとめていただきありがとうございます。動画も繰り返し見て頭にインプットします。

非常にわかり易く解説をしていただき良かったです。非上場株式の相続時の法定相続分の考え方には間違えて理解するポイントがある事を教えていただきました。遺留分の考え方についても正しい理解が出来ました。事業承継にかかわる問題点について話をさせて頂ける先をいくつか(何社か)イメージ出来ましたので、話をしに伺ってみようと思います。


自社株について相続発生時の問題点、又、遺留分対策等について大変解り易く学べた。遺留分の侵害額の計算方法も具体的事例に基づき教えて頂け理解出来た。又、生命保険の活用方法や注意点も学べ代償金の対策としての生命保険の利点を再認識出来た。


図や具体的な数字をふまえて説明いただいたので非常に分かり易く、理解が深まりました。自社株承継については多くのお客様が悩まれている所ですが、生前贈与での対策が散見され、遺留分まで考えていない、あるいは今日も説明いただきましたが、遺留分の算出する株価は相続発生時というのが、分かっていない方も多く見受けられます。私の知識も中途半端ですので、しっかり学び、実例に触れ、専門家の方のアドバイスをいただきながら、自分のものとしていきたいと思います。本日はありがとうございました。


生前対策のない自社株の相続が発生した際に生じる問題について、わかりやすく解説していただき、あらためて知識の整理をすることが出来ました。又、生前対策の手法として、見た目のかっこいい専門家っぽいテクニカルな種類株式や信託という手法の盲点、デメリットを解説していただき、理解を深めることが出来ました。税法では、贈与時の価値で計算するが、遺留分の財産評価は、相続時の価値で算出するという点は、注意が必要だと認識できました。「事業承継のための民法特例制度」については、固定合意や除外合意といったこれまで知らなかった内容でしたので、これを機に勉強して実務で使える知識にしたいと思いました。


自社株式の承継と遺留分対策というテーマで、また遺留分の総論という点から具体的な実例をもとに計算方法を示していただいた。今まで理解していたつもりであったが解釈に一部相違があったので大変参考になりました。取引相場のない中小企業の自社株の相続について適正な対策をとっていなかった時の様々なリスクや、世の中で言われている対策の盲点等、勉強になった点が多かった。相続事業承継分野は、我々の業界でも、レッドオーシャンになってきているマーケットであるが、正しい知識を持ち適切なコンサルをしたうえで対策手段の一環として生命保険の活用提案をしていかねばと強く感じました。


自社株式を生前対策せず相続が発生してしまうとどんな問題が起こるのか、後継者にどの様に承継したら良いのか、遺留分の問題も含め、色々な対策を整理できて良かったです。とても勉強になりました。ありがとうございました。

10ページのように株が準共有となることは初めて知りました。あらためて遺留分侵害額の計算方法はわかりやすくクライアントにも話ができます。民法特例制度について聞いたことはあったが、内容まで理解していなかったが今回のセミナーで理解できました。


生前対策をしていなく自社株を相続した場合、1株ごとに共有財産になること。自社株贈与の遺留分評価は死亡時になることなど、対策してない自社株贈与毎年行っている事業所が多々あり情報提供を必ずしておかなければならない事だと強く感じました。


後半はとても良かったです。実務上の話をいくつも聞けたので、流石、永吉先生です! 和解するためのフックとしての裁判もあるのか~と知る事ができ、納得しました。役員死亡退職金が相続財産になり得るのは盲点だったので知る事ができて本当に良かったです。有難うございました。一日研修のDVD、まだ見ていないので、ちゃんと勉強します!


遺留分対策。自社株の相続は株数を分割するのではなく、1株ごとに共有することになるというお話は、盲点だと思う。相続人が複数いる場合は、遺留分対策が必要だと痛感した。遺留分対策としては生命保険が最も有効であると理解できた。受取人固有の財産であるが、特別受益には注意したい。


生前対策のない自社株の相続は持分比となることは初めて知った。遺留分に関し詳細の説明がありわかりやすかった。事業承継のための民法特例制度は初めて知った。現場の弁護士先生の講義なのでわかりやすかった。民法上と相続税法上の保険金の扱いが、明確に理解できた。

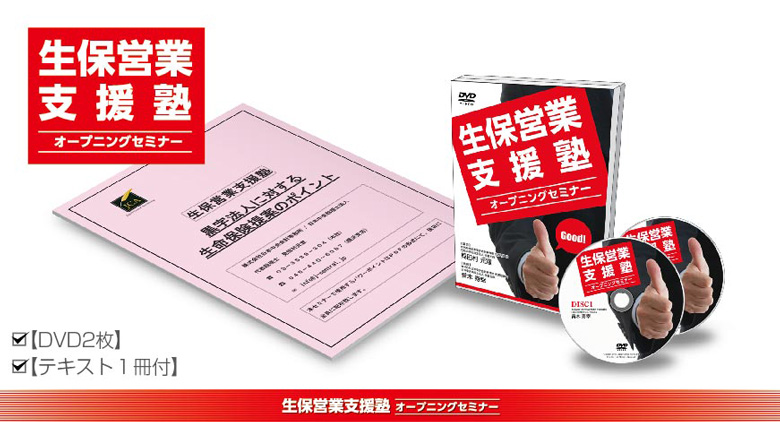
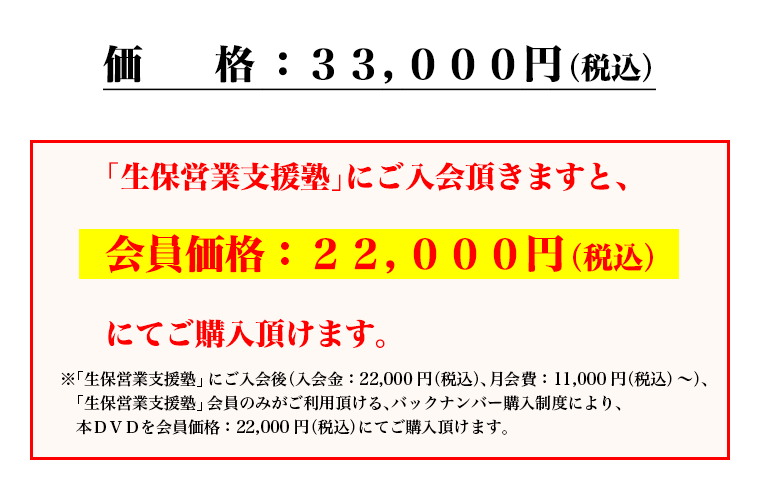
商品はご注文を頂いてから、弊社3営業日以内の発送を原則と致しますが、受注生産のため、在庫が無い場合はご注文日を除いて、弊社5営業日以内に発送致します。