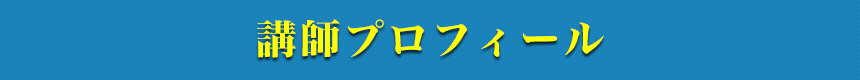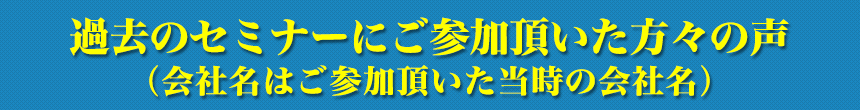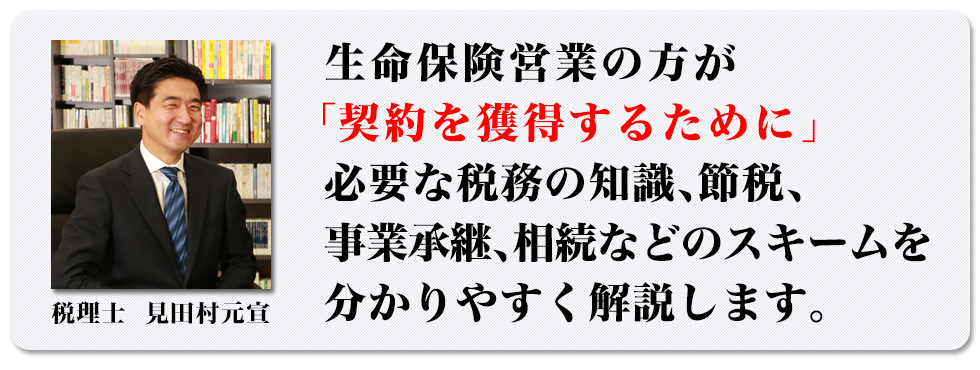
まずはダイジェスト動画をご覧ください(画面をクリックすると再生します)。
- 株式に信託設定しても贈与や売買とは違い、取り戻すことができる
- 分散している株式の議決権のみを信託で集めるときの留意点とは?
- 一般社団法人を受託者とするならば、契約時に受益者を変えておく
- 銀行の信託口で管理すれば、相続財産に含めてしまうミスは防げる
- 親族外承継するときの中継ぎが必要となる場面で、信託が使える

金森 健一 (かなもり けんいち) 弁護士
金森民事信託法律事務所 所長弁護士
駿河台大学法学部特任准教授
信託会社(信託専業会社)にて、設立・運営業務(ライセンス取得、当局対応、コンプライアンス)、商事信託業務(ストラクチャーの構築・契約書起案、受託者としての第三者との取引交渉等)、民事信託(家族信託)に関する設定支援・運営助言業務等に関する各法務に従事。2021年4月より、信託に特化した法律事務所を開設。商事信託実務が得意とする緻密さ・厳格さを、民事信託特有のリスク・コントロールに応用することを強みとする。著書に、「よくわかる民事信託-基礎知識と実務のポイント」(ビジネス教育出版社、共著)などがある。
セミナー動画をご覧頂いた方のアンケート(5段階評価)の集計結果です。


今までは、信託のしくみについてのお話しばかりでしたが、実際の実例も増えてきているということもあるのか、実例を元にしたお話しはとても分かりやすく、理解しやすかったです。メリット、デメリットをどの様に活用して信託を有効活用できるのかが見極めの難しさなのだと分かり、使える方、使えない方を見定めないといけないと考え方を改めました。保険の活用はやはり必須であるなと思いました。きれいに完了させる為のお金の準備は大切で、合わせてのご案内の大切さを感じました。本日はありがとうございました。


信託を活用する事により、相続、事業承継の対策として経営権と資産の分離ができる事、オーナーが生存中に権利移転が出来るというのは強みだという事がわかりました。また、株式移転の費用がかからない、委託者から受託者への譲渡については、無償、非課税というのは活用できると思います。


先月に引き続き、民事信託(家族信託)について、企業オーナー向けに事業承継対策への活用例を学ぶことができた。相続事業承継における民事信託とその他のスキームとの比較から、それぞれのメリットデメリットを解説いただき、6つの事例研究から、信託のメリットを十分発揮できるケースについて理解することができた。円滑でスムーズな事業承継のため、信託は非常に有効なツールのひとつだと思いました。顧客への情報提供の一環で活用していきたい。


事業承継を実行したいときには、信託と生命保険を組合わせて行うと様々なパターンの事業承継ニーズに対応できるのではないかと感じました。ただし、信託制度を利用したい場合は、その専門家とタッグを組んで行うのがベターであるとも感じました。いずれにしろ、信託と生命保険の相性は良さそうなので、積極的に信託制度の利用を行い、生命保険の販売につなげて行きたいと思います。


事業承継での信託利用のメリットとして、特定の財産(自社株)だけ承継先を決めておくことができる(遺言書だと全財産について書くのが一般的)という点を確認できました。信託と生命保険の活用についても、複数の事例を交じえてお話しいただき理解が深まりました。遺留分対策としての保険活用、株式を集約するための保険活用等々、経営者のお客様や税理士さんにもお伝えしていこうと思いました(この話をきっかけに顧問先を紹介してもらえたらと思いました)。

民事信託の組成については、特別決まった方式ではなく、創造力が大事だと感じました。やはり遺留分の問題は絶対に解決するべきと思いました。これから高齢化する世の中で、認知症のリスクはやはり非常に深刻だと思いました。

前回に引続きセミナーを受講させていただきました。今、事業承継の相談に乗っていることもあり、特に事例がとても参考になりました。「早めに贈与しておくための信託」と「生命保険の出番です」がとても参考になりました。信託利用のメリットが良く分かりました。また、留意点も図を使って頭に入りやすかったです。

信託という言葉は何となくは知っていたが、どの様に利用したら良いかということが理解できました。また、生命保険との相性が良いということも理解できました。法人のお客様との会話で、事業承継というワードが出てきた際には、話しをしてみようと思います。


事業承継において信託活用が必要なケースは今後でてくると思っていました。経営者にどのように伝えるのかがいいのか具体的なイメージがうきにくかったが、金森先生の事例は想像がしやすくお客様も何人かイメージがつきました。ただ、受益権等でお金の移動の際の課税をもっと勉強しなくてはならないと思いました。

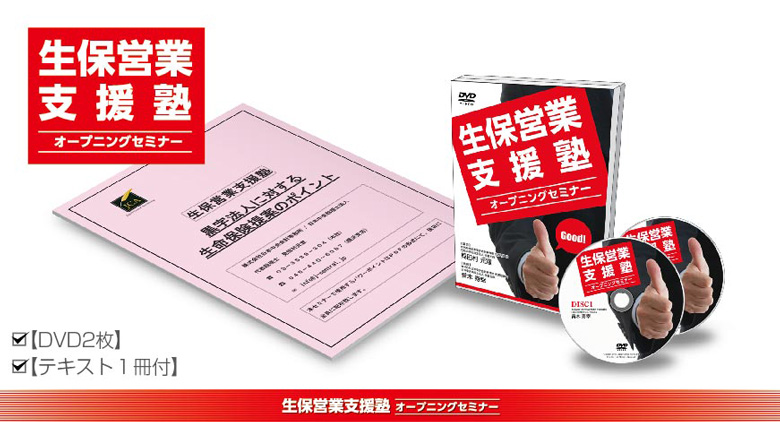
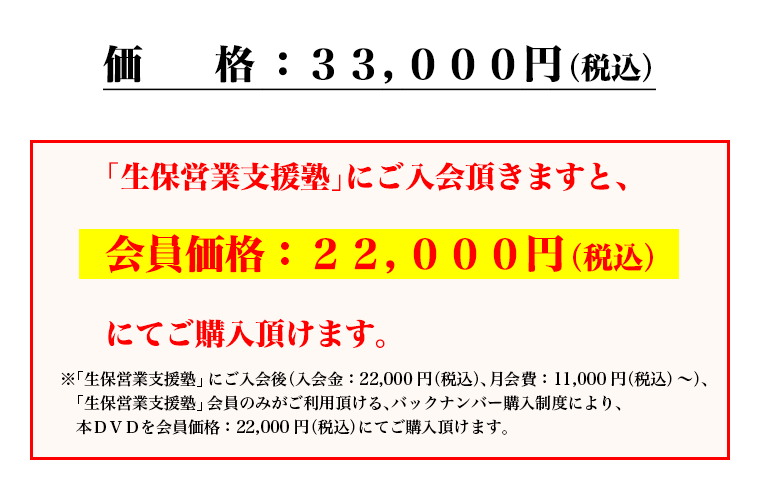
商品はご注文を頂いてから、弊社3営業日以内の発送を原則と致しますが、受注生産のため、在庫が無い場合はご注文日を除いて、弊社5営業日以内に発送致します。